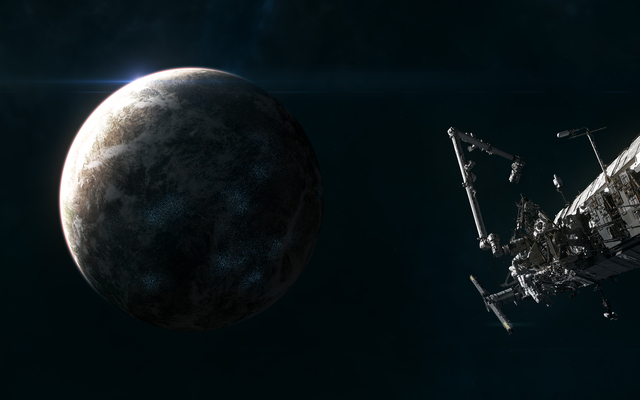再開発される前に見ておきたい!デパート初心者に贈る「老舗百貨店のレトロな『映えスポット』めぐり」
2021年6月、近い将来「日本橋三越本店」と「伊勢丹新宿本店」の再開発に着手する意向を表明しました。どちらも文化財級の歴史ある建築物であり、再開発によって姿を変えてしまう可能性もあります。今しか見られない老舗百貨店のレトロな映えスポットを都市商業研究所の若杉優貴さんが解説します。 2021年6月、大手百貨店「三越伊勢丹ホールディングス」が近い将来「日本橋三越本店」(中央区)と「伊勢丹新宿本店」(新宿区)の再開発に着手する意向を表明しました。具体的な計画は発表されていないものの、日本橋三越本店は1914年築の本館が重要文化財に指定されているほか、伊勢丹新宿本店も1933年築と文化財級の建物であり、再開発によってどのように姿を変えていくのか注目されます。 こうした老舗百貨店は「店のなかに入るのも敷居が高い」と思う人も少なくないかもしれません。そこで今回は「デパート初心者」のために、これら2つの百貨店の建物のなかで気軽に見ることができる「映えスポット」を1つずつ紹介していきたいと思います。 タイムスリップしたような階段室とステンドグラス。 これは一体どこの百貨店…?(画像:若杉優貴)SNSでも話題!三越のシンボル「天女(まごころ)像」 「三越」は、1673年に呉服店「三井越後屋」として日本橋で創業、1683年には隣接地の現在「日本橋三越本店」がある場所へと移転しました。 現在の本館の建物は江戸時代からの店舗があった場所に1914年に建設されたもので、その後も複数回の改装や増築が行われており、1932年には三越が建設費を負担するかたちで東京地下鉄道(現:東京メトロ)銀座線の三越前駅が設置されて地階と駅が直結。さらに、1935年の増築では吹き抜け空間「中央ホール」にパイプオルガンが登場し、現在も週末を中心に生演奏が行われています。日本を代表する老舗百貨店として様々なメディアに登場することも多く、最近は2021年放送のテレビアニメ「大正オトメ御伽話」に現在の建物が完成した直後(関東大震災被災前)の様子が登場したことも話題となりました。 日本橋三越本店の本館。1912年築、設計は横河工務所(現:横河建築設計事務所)。(画像:若杉優貴) この日本橋三越本店のシンボルとなっているのが、吹き抜け中央ホールに設置された「天女(まごころ)像」。三越の基本理念「まごころ」を冠したこの像は昭和の名彫刻家・佐藤玄々氏により1960年に完成したもので、完成までには10年もの歳月がかかったといいます。 日本橋三越本店の吹き抜け・中央ホールにそびえる「天女(まごころ)像」(画像:若杉優貴) 三越に良く行く人にはお馴染みのこの「天女(まごころ)像」。「都心に良く行く人なら誰でも知ってるでしょ!」と思いきや、初めて入店する人にとってはデパートの店内にこのような大きな像があること自体に驚く人も多いようで、SNSでは「すごい像を見た!」という投稿が話題を呼ぶことも。 「日本橋の三越といえば高級品ばかりで入りづらい…」と思うかも知れませんが、この中央ホールがあるのは化粧品やハンカチなどの売場の横。中央ホール内には椅子も設置されているため、像を下から座ってゆっくり眺めることもできます。お客さんが多く訪れる売場に面しているため、記念撮影の際は店員さんにひとこと声を掛けることをお忘れなく。 そして、「天女(まごころ)像」を下から眺めたあとは、吹き抜けの階段を昇りながら緻密な細工を間近に眺めてみましょう。 下から見上げた佐藤玄々氏による「天女(まごころ)像」。 繊細な彫刻とその迫力に圧倒。(画像:若杉優貴) なお、三越のウェブサイトには中央ホールのもう1つのシンボルである「パイプオルガン」の生演奏が行われる日程も掲載されています。生演奏の曲目はクラシック曲が中心ですが、2020年には人気ゲーム・アニメ「艦隊これくしょん」とのコラボ曲集が、また2021年秋にはJ-POPなどの「年代別ヒット曲集」が演奏されるなど、様々な企画がおこなわれることも。もし時間が合うならば演奏中に訪れるのも良いですし、像を静かに観賞したいなら演奏が無い日を選ぶのも悪くないでしょう。 伊勢丹建設当時の数少ない面影―屋上の陽が差し込む「ステンドグラス」 「伊勢丹」は、1886年に神田旅籠町(現在の昌平橋近く)で「伊勢屋丹治呉服店」として創業、1933年に新宿三丁目に建設された現在「伊勢丹新宿本店」となっている建物へと移転しました。 ちなみに、新宿三丁目交差点側の建物の正面部分は1925年に建てられたライバル百貨店「ほてい屋」として開店したもの。伊勢丹が1935年にほてい屋を買収、1936年に2つの百貨店の建物が接続されて正面部分がほぼ現在のかたちになり、さらに1957年には都電車庫跡地を取り込むかたちで裏側にも増築されています。 伊勢丹新宿本店。1933年築、設計は清水組(現:清水建設)。 実は交差点に面する部分はもともと別の百貨店でした。 (現在は縦のネオン看板が撤去されています)(画像:若杉優貴) 伊勢丹新宿本店の外観は建築時の面影を色濃く残す反面、その内装については幾度もリニューアルを繰り返しているためかつての面影は少なく、また日本橋三越本店の「天女(まごころ)像」や「ライオン像」のようなシンボル的存在もありません。 そんな伊勢丹新宿本店において「最も歴史を感じさせられる場」が階段室です。とくに、屋上庭園へと上がる階段にある季節の花や蜻蛉で彩られたステンドグラスは、明治に創業した日本のステンドグラスの祖というべき「宇野澤ステインド硝子工場」が手掛けたもの。若干色褪せてしまっているものの、それが建物の歴史とともに名門百貨店らしい「上品さ」を感じさせてくれます。 ステンドグラスのある重厚な階段室。 売場の喧騒とは別世界。優しい光に包まれてタイムスリップしたような気分に。(画像:若杉優貴) ステンドグラスを見たあとは、季節の花々で彩られる屋上庭園「アイ・ガーデン」に出て防火の神様「朝日弁財天」にお参りしたあと、その横にある創業者・小菅丹治像にもご挨拶を。 屋上庭園には季節の花々に囲まれた伊勢丹創業者・小菅丹治像が。(画像:若杉優貴) 今回は初心者向けに気軽に撮影しやすい注目スポットを1つずつ紹介しました。このほかにも、両店ともに階段室の大理石部分に化石がみられるなど、店内外にはまだまだ多くの「歴史的見どころ」があります。 こうした老舗百貨店では、新型コロナウイルスの感染拡大前には定期的に建物の見どころを紹介する館内ツアーが行われていた店舗も少なくありません(現在不定期実施している店舗もあるため、詳しくは店舗へ確認を)。 もし百貨店の歴史に興味を持ったならば、そうした館内ツアーの開催日を調べて参加してみることもオススメします。 日本橋三越本店にある「地下鉄入口」の案内。 百貨店には隠れたおしゃれなレトロスポットが沢山。(画像:若杉優貴)参考:三越 編(1990年)「三越85年の記録」株式会社三越
- おでかけ
- 三越前駅
- 新宿三丁目駅
- 新宿駅