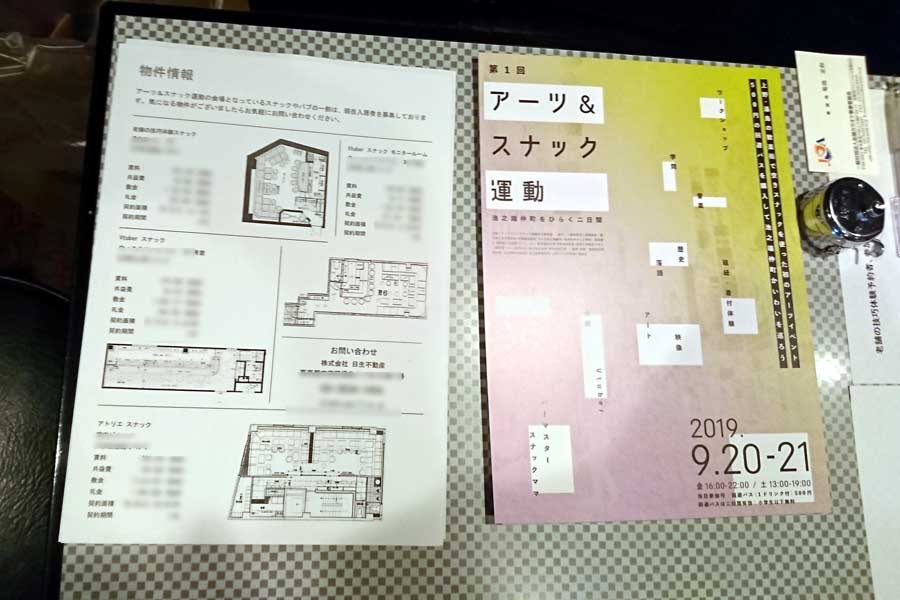神宮前に「○○が創る」東急プラザ誕生!地下には意外な「高円寺の人気店」も
2024年春、「東急プラザ表参道原宿」の斜め向かいに「東急プラザ原宿『ハラカド』」が開業します。それに先立ち、「東急プラザ表参道原宿」5階フロアも新たな文化発信拠点としてフルリニューアル。都市商業研究所の若杉優貴さんが、2つの施設が目指す姿からユニークな試みまで解説します。神宮前2店舗目の東急プラザ「ハラカド」誕生 渋谷区の表参道・神宮前交差点に、複合商業施設「東急プラザ原宿『ハラカド』」(以下「ハラカド」)が2024年春に開業します。 東急プラザといえば、神宮前交差点にはすでに2012年4月に開業した「東急プラザ表参道原宿」があり、館内には多くのコスメ・アパレルショップが軒を連ねていますが、「ハラカド」はこれまでの東急プラザとは大きく異なる「体験型」の店づくりを特徴とします。 神宮前交差点に建設中の「東急プラザ原宿『ハラカド』」。(画像:若杉優貴)【画像】トップクリエイターたちが文化を醸成してきた神宮前の新しい拠点!>> ハラカドは「クリエイターが創る」東急プラザ 「ハラカド」は地上9階・地下3階・塔屋1階建てで、ガラス張りの印象的な外観は新型カプセルホテル「ナインアワーズ」を手掛けたことでも知られる建築家の平田晃久氏によるものです。 この場所にはもともと複合マンション「オリンピアアネックス」や、創業100年の老舗洋菓子店「コロンバン本店」などがありましたが、再開発のため2020年に解体されていました。 なお、ハラカドの開業に併せて、現在の「東急プラザ表参道原宿」もリニューアルし、「東急プラザ原宿『オモカド』」(以下「オモカド」)に改名するとしています。 再開発前のオリンピアアネックス・コロンバン周辺。(2018年)(画像:若杉優貴) ハラカドの最も大きな特徴となるのが「さまざまなクリエイターによる店づくり」。 運営する東急不動産によると「オモカド/ハラカド」は「人々が出会い、新しい文化を生み出す『かど』をめざす」ことを標榜。館内はさまざまな「クリエイター」がプロデュースし、クリエイターが文化を生み出して発信する場となり、そしてその文化に共感・共鳴する人々が集まることで、ハラカドから新しい文化が生まれることをめざすとしています。 「ハラカド」イメージロゴ。館内に入居する「れもんらいふ」千原徹也氏によるもの。(東急不動産ニュースリリースより) その中核を担う存在が、ハラカドのテナントで構成・運営されるクリエイティブコミュニティ「ハラカド町内会」。町内会にはデザイン事務所「れもんらいふ」のアートディレクターで映画監督の千原徹也氏、レストラン「sio」シェフの鳥羽周作氏、高円寺の老舗銭湯・小杉湯の平松佑介氏、クリエイティブ・ディレクターの大木秀晃氏ら、さまざまなクリエイターが参画し、町内会によるコミュニティづくりが店舗の運営に活かされることになります。 「ハラカド」に入居するクリエイターたち。(東急不動産ニュースリリースより)「体験型」東急プラザ、地下に「高円寺の人気銭湯」も! ハラカドは個性派クリエイターが手掛けるだけあって、館内構成もこれまでの東急プラザとは一味も二味も違う内容。モノを売るのみではない「体験型」の店舗が多く出店することも特徴で、その象徴といえるのが、地階に入居する銭湯「小杉湯原宿(仮称)」です。 小杉湯原宿を運営するのは高円寺で人気を集めている銭湯「小杉湯」。1928年創業の老舗銭湯でありながらさまざまなイベントやコラボレーションを行うことでも知られ、この夏も流しそうめんや甘酒風呂を実施。ハラカドに生まれる古くて新しい銭湯でも、こうした季節に合わせるかたちのイベントや館内クリエイターとのコラボが行われることになるでしょう。 表参道から見た東急プラザ原宿「ハラカド」。 物販のみならず「コト消費」「体験型」店舗が多く出店。写真左上の緑化部分には屋上テラスが設けられます。(画像:若杉優貴) ハラカドには、このほかに「文喫」を手掛けた日販による古い雑誌を集めたアーカイブ図書館「COVER」(雑誌寄贈者募集中!)、千原徹也氏らクリエイターが厳選した品を来館者に紹介・販売する「クリエイターズマーケットフロア」、セルフカフェ併設の会員制ラウンジ「Coffee Brew Club」、千原徹也氏が手掛ける「そこにクリエイターがいる」をコンセプトにしたデザイン事務所「TOKYO DESIGN STUDIO」など、やはりさまざまな機能を備えた体験型の店舗たちが軒を連ねる予定となっています。 飲食フロアには、ミシュラン1つ星レストラン「sio」の新業態店「FAMiRES」が新時代のファミリー(=仲間)レストランとしてオープンするほか、ビーガン料理専門店「FALAFEL BROTHERS」やローマ発のジェラート店「Giolitti」など話題のお店も出店予定とのこと。 その他フードコートには約20店が軒を連ねる予定(画像:東急不動産ニュースリリースより)「オモカド」には早くも「ハラカド」の雰囲気を味わえるフロアが登場 ハラカドの開業に合わせて「東急プラザ表参道『オモカド』」への改名を発表した「東急プラザ表参道原宿」では、8月1日に5階フロアを「LOCUL(ローカル)」としてフルリニューアルしました。 「東急プラザ表参道原宿」は来年2024年春に「東急プラザ表参道『オモカド』」に改名される予定。 それに先駆けて8月、5階フロアが「LOCUL(ローカル)」としてリニューアルオープンした。(画像:若杉優貴) このローカルのフロアの大きな特徴は、区画を1㎡から月極(つきぎめ)料金で契約・利用できる「サブスクリプション制」であること。フロア内には生花店、レコード店、アパレルといったさまざまな業種のブースが集結。なかには写真展やアトリエなど、展示を主目的とした区画も。 ローカルのフロアは店舗間の仕切りがなく開放的な雰囲気で、出店する人たち同士がフリーマーケットのように交流を図りやすいことも特徴。東急不動産はこのローカルを「体験・共感・共創を生むコミュニケーション」ができる空間と位置付けており、「ハラカドの雰囲気を一足先に体験できる場」であるともいえるでしょう。 明治通り・神宮前交差点から見た「ハラカド」(左)と「オモカド」(右正面)。 数年にわたる歩道拡張と交差点改良によって歩行者環境も改善されています。(画像:若杉優貴) ハラカドの建設と前後して、明治通りと神宮前交差点では歩道の拡張と交差点の改良が実施されており、以前よりも歩きやすい街となりました。 「もう何年も神宮前に行ってない!」という人は、渋谷方面から2020年7月に開業した「レイヤード・ミヤシタパーク」(宮下公園)を経由するかたちで、明治通りを歩いて訪れてみることをオススメします。 ハラカド外観イメージ(画像:東急不動産ニュースリリースより)■東急プラザ原宿「ハラカド」(2024年春開業) 住所:東京都渋谷区神宮前6-1000 営業時間:未定 アクセス:東京メトロ千代田線・有楽町線「明治神宮前〈原宿〉駅」7番出口すぐ ■東急プラザ表参道原宿(2024年春より“東急プラザ表参道「オモカド」”に改称) 住所:東京都渋谷区神宮前4-3-3 営業時間:11:00~20:00 アクセス:東京メトロ千代田線・有楽町線「明治神宮前〈原宿〉駅」エレベーター専用出入口前すぐ
- スポット
- 原宿