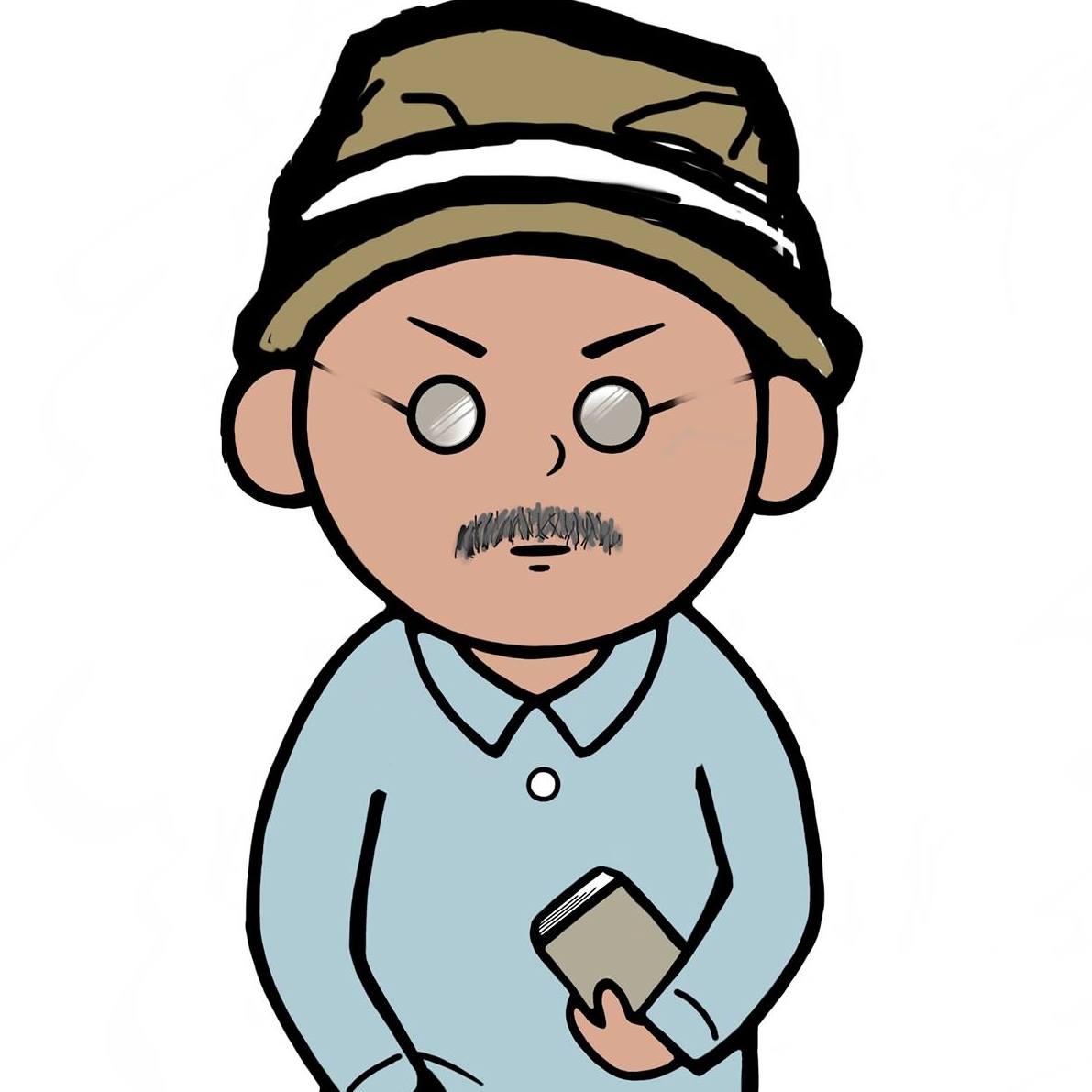渋谷の『穴場』発見!出勤前に立ち寄りたいおすすめモーニング4選
起きたら着替えて職場に直行・・・そんな慌ただしい朝が続くと、ストレスもたまるもの。フレッシュな気分で仕事に向かえる、おすすめ渋谷モーニング4選を、フリーランスライターの岩本信彦さんがご紹介します。 東京で忙しく働いている方々にとって、朝の時間は貴重です。 この時間を有意義に過ごすことで、一日のスタートが決まるといっても過言ではありません。 かつての筆者も睡眠時間を確保するために、出社時刻ギリギリまで寝ていましたが、朝が慌ただしくなるとストレスを感じることも多かったです。 そこで生活を改善しようと、起床から20分〜30分で支度をして職場に直行するという生活を見直しました。 すると生活の質が大きく向上し、ストレスも減りました。 そんな朝の時間を有効に使うためにも、会社の近くで朝食を取ることを習慣化してみてはいかがでしょうか。 モーニングの時間を取ることで気持ちにも余裕が生まれるはず。 そこで本記事では、渋谷で働く方々におすすめのモーニングが食べられるお店を紹介します。 BUY ME STAND(バイミースタンド)渋谷店 並木橋の交差点から八幡坂を少し上ると、左手に見えてくるのが「BUY ME STAND(バイミースタンド)」です。 渋谷駅からは少し離れますが、駅前の喧騒(けんそう)が苦手な人にはおすすめです。 「BUY ME STAND(バイミースタンド)」はライフスタイルブランドの「SON OF THE CHEESE(サノバチーズ)」の店舗に併設される形でオープンしました。 ターコイズを基調としたスタイリッシュな内装に、アメリカンなサンドイッチ。 Instagramでも話題を呼び、若者に人気です。 トッドインザホール(画像:岩本信彦) 厚切りのトーストにたっぷりのチーズとたまご。 朝からガッツリ食べたい人であれば、食欲をそそるビジュアルではないでしょうか。 またコールスローもついているので、野菜が取れるというのも嬉しいポイントです。 CHIMNEY COFFEE(チムニーコーヒー) 玉川通り沿いのセルリアンタワーからほど近い小さなコーヒーショップ、「CHIMNEY COFFEE(チムニーコーヒー)」。 もともとグッズショップとしてスタートし、今はコーヒー屋として営業しています。 コンパクトな店内でコーヒーと軽食が楽しめるので、ちょっとした休憩には最適です。 桜ヶ丘町にあるので、喧騒を避けたい人やコーヒーだけテイクアウトするのも良いでしょう。 特にクロワッサンにたまごペーストを挟んだ、たまごサンドがおすすめ。 たまごサンドとアイスコーヒー(画像:岩本信彦) 食パンベースの昔ながらのたまごサンドも良いですが、こちらも負けてはいません。 バターの風味豊かなクロワッサンと、たまごペーストの相性の良さを感じられるはずです。 VALLEY PARK STAND(ヴァリー・パーク・スタンド) ホテル「sequence MIYASHITA PARK」と「宮下公園」を結ぶ「VALLEY PARK STAND(ヴァリー・パーク・スタンド)」。 ホテルの宿泊者以外の一般のユーザーも利用できるカフェです。 モッツアレラ&トマト&バジルのパニーニとコーヒー(画像:岩本信彦) ガラス張りなので、明治通り沿いのビルや、MIYASHITA PARKの緑を眺めながらゆったりと過ごすのがおすすめです。 筆者も渋谷で仕事をしていた経験がありますが、多くのビルの上部階がどうなっているかは知らなかったので、カフェからの景色は新鮮でした。 平日は比較的空いているので、テレワークなどにも良いでしょう。 金のおにぎりと天白のかつお出汁 かつおとぼんた パン中心のモーニングメニューを紹介してきましたが、「朝はやっぱり和食でしょ」という人も多いはず。 そんな人におすすめなのが「かつおとぼんた」です。 Googleの日本法人の本社が入っていることでも有名な渋谷「渋谷ストリーム(SHIBUYA STREAM)」に入っているおにぎり屋です。 朝の8時から営業しており、ダシの効いた味噌汁とかつおの香り豊かなおにぎりが楽しめます。 おにぎりとお惣菜のセット(画像:岩本信彦) 初めて訪れる人は、かつおの風味を楽しめる「天白のおかか」がおすすめです。 夜はお酒も飲めるので、仕事帰りに軽く飲みに行くのも良さそうです。 朝は渋谷でゆったり過ごしてみませんか? 朝に時間をとって陽の光を浴びたり、ストレッチをしたりすることで自律神経も整いやすくなりますが、毎日決まった時間に朝食を取ることも効果的です。 そんな習慣を作るためにも、ぜひモーニングを活用してみましょう。 いつも人が多く、せわしなく見える渋谷ですが、朝の落ち着いた時間帯に訪れるとまた違った雰囲気を味わえます。 習慣化するまでは時間がかかるかもしれませんが、まずはいつもより30分早く起きて、渋谷に出かけてみてはいかがでしょうか。
- カフェ・スイーツ
- 渋谷駅