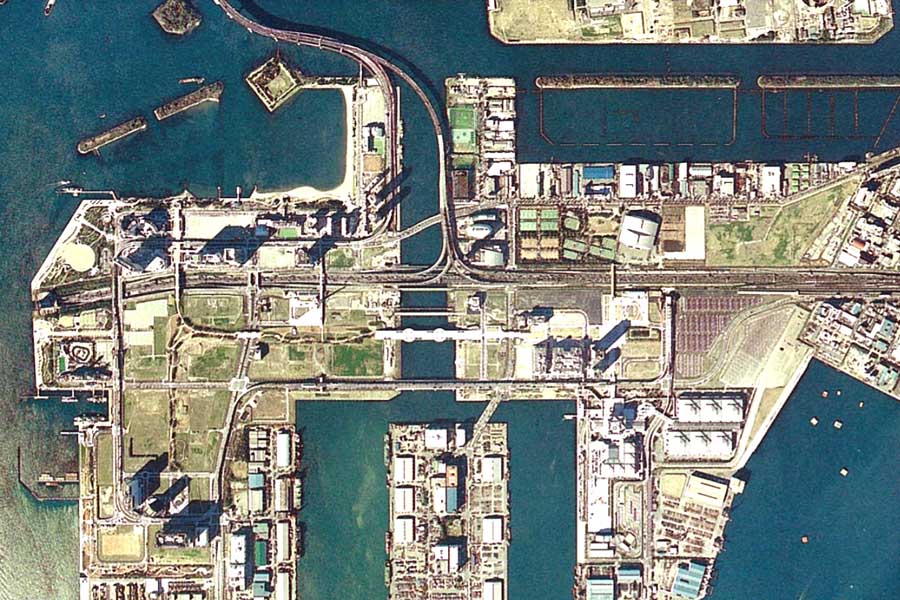都下に立ち並ぶ一戸建て なぜ日本人は「持ち家」を目指し続けるのか?
いまだ「持ち家」信仰が根強い日本。その理由について、ブログ「山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期」管理人の山下ゆさんが解説します。根強い「持ち家」信仰 東京の都心からJRや私鉄に乗って郊外へ向かえば、途中から一戸建てが隙間なく立ち並ぶ光景が目につきます。なぜ東京の景色はこのようになっているのでしょうか? そして、家といえば ・持ち家派 ・賃貸派 の対立がメディアでよくとり上げられますが、日本では多くの人が持ち家を目指しています。これはなぜなのでしょうか? 都内の「持ち家」イメージ(画像:写真AC) このふたつの疑問に答えてくれるのが、今回紹介する平山洋介『住宅政策のどこが問題か』(光文社)です。わが国の住宅政策をさかのぼることで、人びとがいかに「家を持つこと」に対して動機づけられるようになったのかがわかります。 著者は戦後社会の特徴のひとつを「持ち家社会」だとしています。これは持ち家が多く、多くの人が持ち家の取得を目指す社会で、賃貸住宅から持ち家へ、小さな住宅から大きな住宅へ、マンションから一戸建てへと住まいの「はしご」を登っていくような社会です。 もちろん、近年ではタワーマンション人気などもあって必ずしも一戸建てがゴールにはならなくなってきていますが、それでも最終的には家を所有して落ち着きたいと考えている人は多いでしょう。 ところが、戦前はそうではありませんでした。1941(昭和16)年の都市部における持ち家率は22.3%にすぎず、残りは公営や民営の借家でした。しかし、戦後になると持ち家率は60%程度まで上がり、それが続いていくことになります。 戦時下と戦後の地代家賃統制令によって、大家にとって借家経営のうまみはなくなってしまい、借家の払い下げが進んだのです。 日本の住宅システムは「アングロサクソン型」日本の住宅システムは「アングロサクソン型」 持ち家率が高いまま推移した理由は、これだけではありません。 他国では福祉国家の建設とともに公営住宅の整備が進みましたが、日本ではこれが弱いままでした。福祉政策と住宅政策は切り離され、政府は低所得者層向けの住宅供給には力を入れず、中間層向けの持ち家取得を支援する方向に集中しました。 諸外国を見ると、イギリスやアメリカといったアングロサクソン諸国では持ち家率が高く、フランス、ドイツ、北欧などの大陸ヨーロッパ諸国では持ち家率が低くなっています。 欧米の「持ち家」イメージ(画像:写真AC) アングロサクソン諸国では、低所得者層向けの公営住宅を除けば、あとは基本的に市場に任されています。一方、大陸ヨーロッパ諸国では、政府・自治体・公的機関・民間非営利組織などさまざまな主体が借家を供給しており、その家賃は低く抑えられています。 日本の住宅システムも基本的にはアングロサクソン型ですが、少し違う点が企業による ・社宅などの住宅供給 ・家賃補助 の存在です。また、住宅政策が「家族」と結び付けられ、「家族」を支えるために住宅政策が展開されてきました。 公営住宅に関しては、アングロサクソン諸国と同じように低所得者層向けのものでした。特に1959(昭和34)年の公営住宅法の改正で、収入超過者からの「明け渡し努力義務」を導入し、所得が一定水準を超えれば公営住宅に住むべきではないという方針を明確化しています。 公営住宅の数自体も60年代までは増加しましたが、70年代からはほぼ一貫して減少し、その代わりに民間の賃貸住宅が需要を吸収することになります。 ただし、民間の賃貸住宅の家賃は値上げが難しかったこともあって、地価に比べるとその伸びは抑えられます。家主は住宅修繕への投資を控えることになり、民間の賃貸住宅の質は低いままにとどまりました。 また、他国にはある民間借家の入居者に対する公的な家賃補助制度も日本ではつくられませんでした。公営住宅に入居できない人との公平性をはかるための制度ですが、日本では公的な家賃補助制度は生まれず、一部の大企業が行うものとなりました。 結果として、人びとは若いときを貧弱な民間の賃貸住宅で過ごし、そこからの脱出を目指して持ち家を目指すことになります。 一戸建てが郊外に立ち並んだワケ一戸建てが郊外に立ち並んだワケ さらに持ち家は経済上のセキュリティーも意味しました。持ち家は多くの人にとってもっとも大きな資産であり、購入時には住宅ローンを背負うものの、その負担はインフレによって実質的に軽減され、所得の上昇によって返済の負担も軽くなっていったからです。 持ち家は安心した老後を過ごすために必要なものでもありました。福祉が手厚いとはいえない日本において、持ち家は老後の生活を支えたのです。 また日本では、建物と土地が一体となって不動産を構成するのではなく、資産価値は土地が中心で、住宅の寿命は短く、その市場価値は経年とともに急速に低下するものでした。 こうなると、資産としては土地が重要になります。結果として、日本では狭い土地であっても自分の土地を求める動きが強くなり、都市の郊外には一戸建てが立ち並ぶことになりました。 都内の「持ち家」イメージ(画像:写真AC) しかし、この持ち家を目指す「はしご」はいたるところで問題にぶつかっています。バブル崩壊後、土地の価格は右上がりではなくなりましたし、デフレ気味の経済によって住宅ローンの負担が実質的に軽減されることもなくなりました。 さらに所得そのものも伸び悩むようになりましたし、大企業の正社員にでもならなければ社宅や家賃補助などの企業による支援も受けられません。非正規雇用の増加もあって、以前のように順調に「はしご」を登っていける人は少なくなっているのです。住宅を相続できる人と相続できない人もいて、住宅をめぐる格差は拡大しつつある状況です。 また、日本の住宅政策はあくまでも「家族」を支援することに重点が置かれ、単身者に対して住宅金融公庫は1980年代まで融資を行っていませんでした。 「成長依存」から「分配」へ「成長依存」から「分配」へ こうしたなかで不利な状況に置かれていたのが、例えば女性の単身者です。著者も参加した2004(平成16)年のアンケート調査では、女性の平均持ち家率は有配偶者で55%であるのに対して(もっとも所有の名義だと「夫のみ」が全体の3/4程度になる)、無配偶者では8%にとどまっています。 このように誰もが持ち家を目指すというライフコースは崩れつつありますが、それでも政府の住宅政策の中心は住宅ローン減税です。さらにこの住宅ローン減税は景気対策の一環としても拡大されており、「はしご」を登れる人と登れない人の格差はさらに開いているともいえます。 こうした状況に対して、著者は ・営利を目的としない公的な性格を持つ賃貸住宅の拡充 ・民間賃貸住宅に入居する人への公的な家賃補助の導入 などを主張し、「成長依存」から「分配」への住宅政策の転換を訴えています。 平山洋介『住宅政策のどこが問題か』(画像:光文社) 2009年に出版された本で、データ的には少し古い面もありますし、新築、中古ともにマンションに対する評価などはこの10年でずいぶん変わった部分もあるかとは思います。 また新書にしてはかなり硬い文体ですが、本書は今なお通用する日本の住宅政策に対する鋭い洞察に満ちた本です。
- ライフ
- 東京