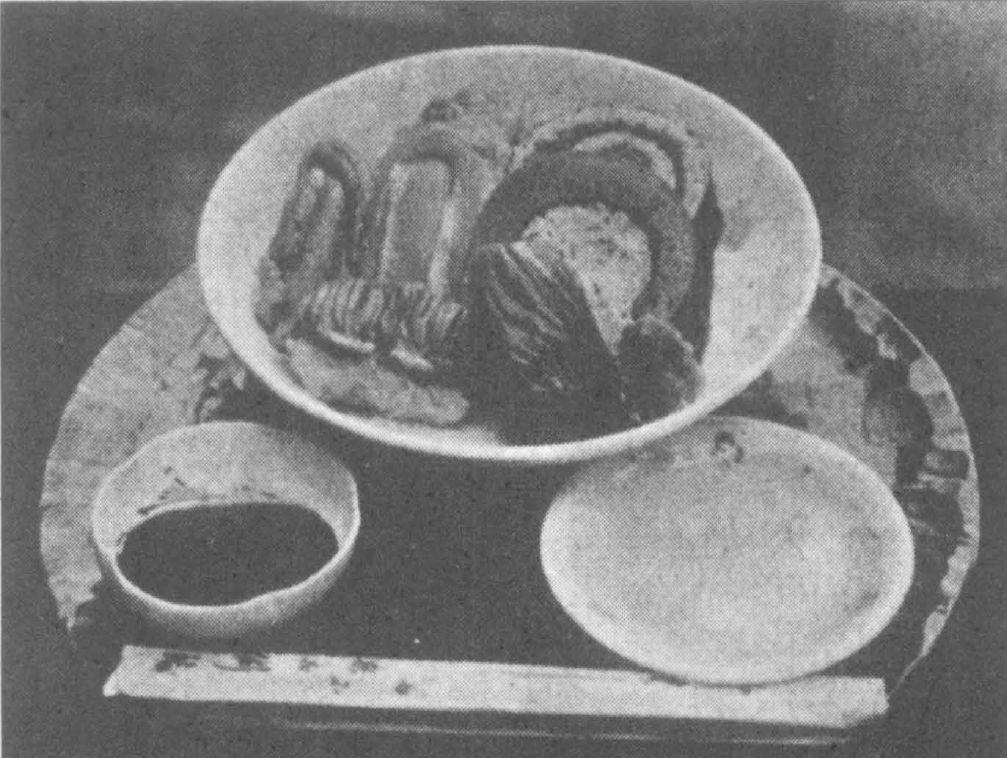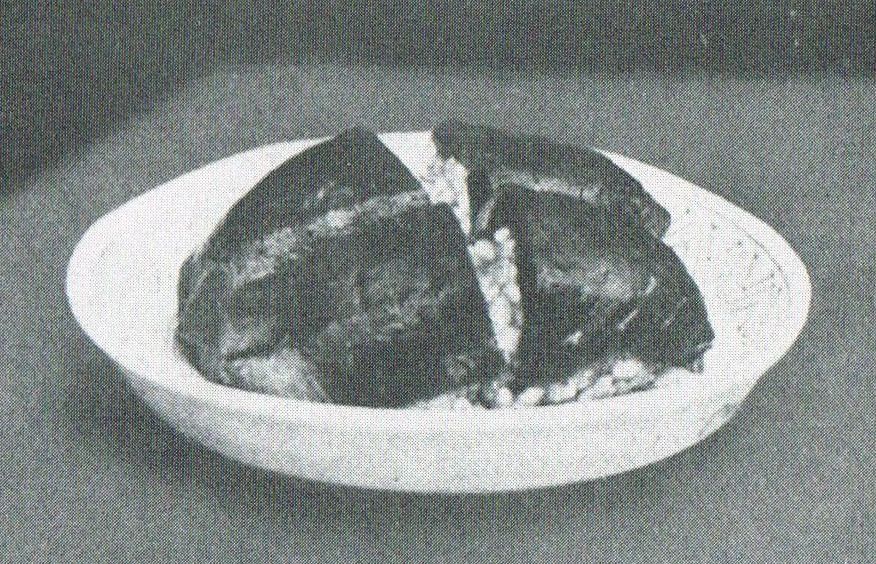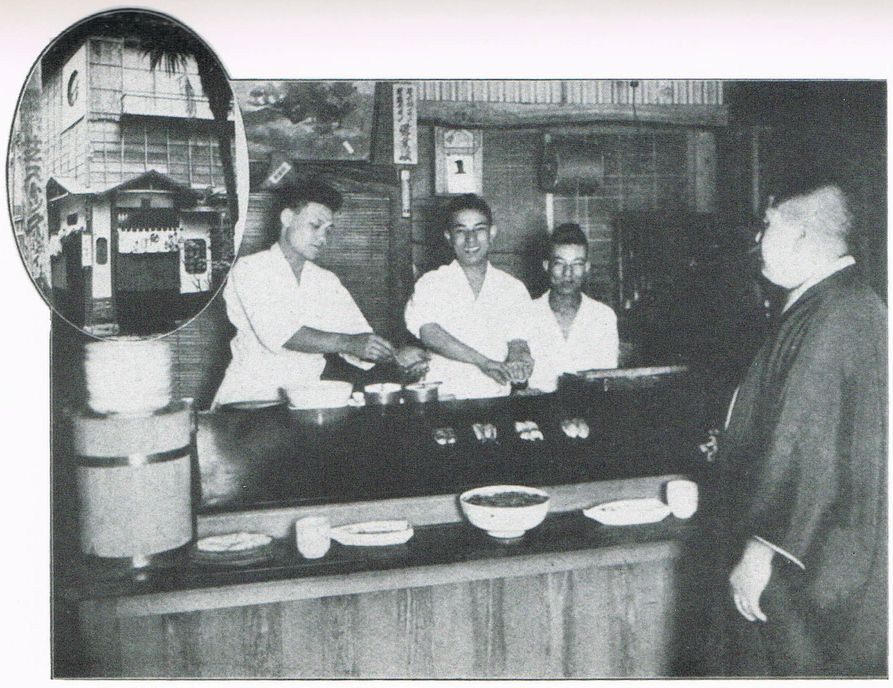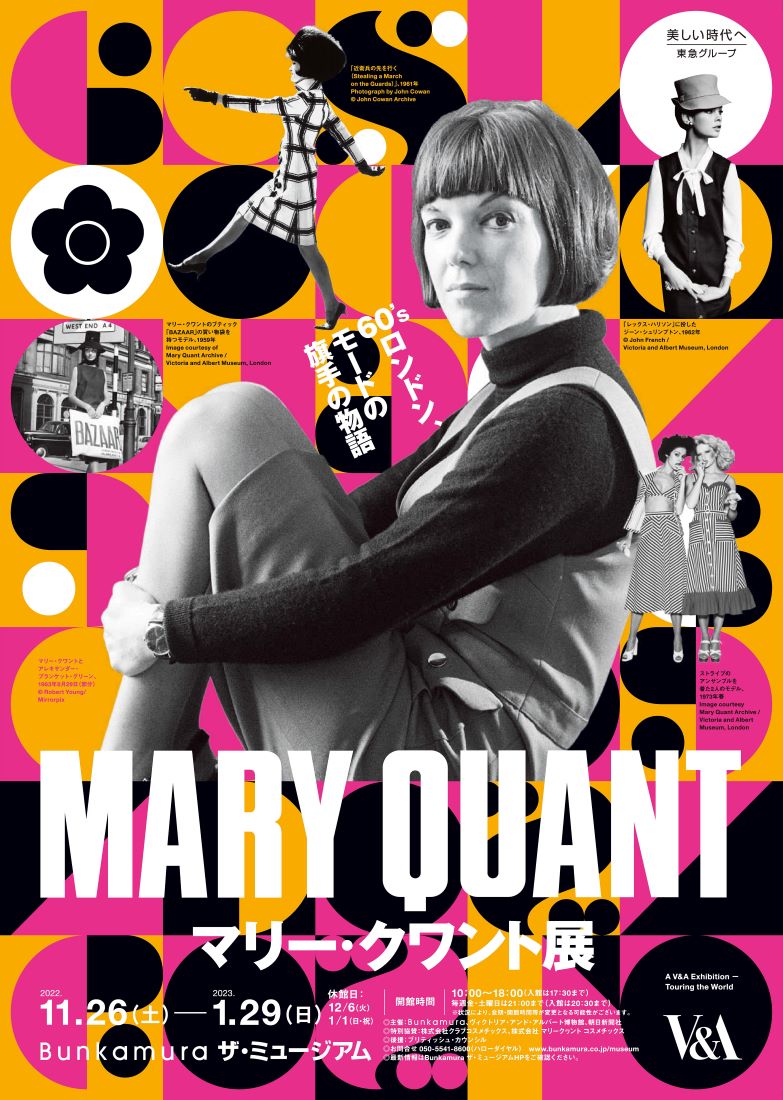【日本橋・早稲田・渋谷】時代劇の舞台で時を重ねる。お江戸東京歴史さんぽ
徳川家康が幕府を開いて420年。経済が大きく発展した要因の一つとして、物流のため江戸という土地を拠点に選んだことにあると考えられています。長寿時代劇にもたびたび登場する歴史の舞台についてエデュケーショナルライターの日野京子さんがご紹介します。 今年の大河ドラマは徳川家康が主人公。戦国時代の大河ドラマでは必ず登場する超重要人物ですが、単独の主役となるのは実に40年ぶりになります。現在の東京が世界的な大都市となったのも、徳川家康が江戸に幕府を開いたからで、今の繁栄も家康のおかげといえるでしょう。 さて、江戸時代を舞台とするドラマと言えば時代劇。昭和の頃は当たり前のようにお茶の間に流れていましたが、地上波での放送はすっかり減少しました。移り変わりの激しい東京都心にも、時代劇の舞台となった地名や場所が現在も残っています。 今回は、時代劇の面影を残す都心のスポットや大人気時代劇『暴れん坊将軍』から生まれた「マツケンサンバⅡ」とのコラボカフェなどをご紹介していきます。 ●【日本橋~東京駅周辺】時代劇でおなじみの八丁堀 日本橋界隈に隣接する中央区八丁堀は、江戸時代の頃に今でいう警察官にあたる与力やその部下である同心が多く住む町でした。勤務先である奉行所は今の東京駅や有楽町駅付近にあり、職場から近い八丁堀に組屋敷があったからです。 東京駅日本橋口周辺には「遠山の金さん」で有名な北町奉行所、有楽町駅南東側には南町奉行所があった(画像:photoAC) 時代劇でも「八丁堀の旦那」と呼ばれるシーンも多く、東京に住んでいない時代劇好きな人にもなじみのある町です。「堀」という字の通り、江戸時代の木材などの物資を運ぶ水路が入り組んでいる場所でしたが、現在は埋め立てられて当時をしのぶものも限られています。 日本橋クルーズ(R)の「お江戸TOKYOクルーズ」では江戸城を守る外堀の役割もあった日本橋川から当時の石垣などを間近に見ることができます。東京観光の定番の一つですが、都内在住だとかえって水際から風景を眺めるような体験をする機会が少ないのでは。水の流れに身を任せる江戸時代の時間感覚を体験してみてはいかがでしょうか。 関東平野の真ん中であり川の終着点が集まる江戸の地は、鎌倉のように山に阻まれることもなく水路を張り巡らし物資を運ぶのに都合の良い土地だった。日本橋から上流へ向かってから川を下る「お江戸TOKYOクルーズ60分」では、江戸城の石垣の一部が残っている場所も周遊。TV番組のようにベテランガイドの解説付きで楽しめる(画像:photoAC)●【新宿区】江戸最大級の大名屋敷を誇る尾張藩跡 数々の大名屋敷があった江戸の町。その中でも最大規模を誇ったのが、将軍家の御三家の筆頭格である尾張藩です。人気時代劇『暴れん坊将軍』の主人公、徳川吉宗のライバル役として登場する徳川宗春は、尾張藩の藩主でした。 大名屋敷は藩主や妻が住む上屋敷、世継ぎなどが住む中屋敷、そしてお付きの者が住む下屋敷と分類されていました。 市ヶ谷の防衛省一帯は尾張藩の藩主や妻子が住む上屋敷だった(画像:photoAC) 尾張家の上屋敷は市ヶ谷にある防衛省一帯、中屋敷が四ツ谷駅近くの上智大学一帯、下屋敷は現在の新宿区にある戸山ハイツや戸山公園を含む13万6千坪の土地を拝領していました。その広さは桁違いの広さを誇り、御三家筆頭にふさわしいものでした。 尾張藩の屋敷跡の中でも、公園として整備されている戸山公園には当時の面影を残す人口の築山「箱根山」があり、大名屋敷のスケールの大きさを体感することができます。 西早稲田駅からほど近い戸山公園。山手線内で最も標高の高い山「箱根山」(画像:photoAC)●【渋谷】時代を超えて「上様」と盛り上がろう 数ある時代劇の中でも人気の高いシリーズの一つが『暴れん坊将軍』です。 松平健さん演じる八代将軍・徳川吉宗が身分を隠して江戸の町で起きる事件を解決する時代劇は1978年から2002年にかけてレギュラー放送された長寿番組でした。 家紋風の焼き印入りどら焼きが乗った和パフェなど、トロピカルメニューと和の融合が楽しい(TOKYO PARADE goods&cafeプレスリリースより) 俳優としての地位を確立した松平健さんは歌手としても活動し、2004年に大ヒットした『マツケンサンバⅡ』は長い間幅広い年齢層から人気を集めています。そんなマツケンサンバの世界が渋谷パルコ6階の 「TOKYO PARADE goods&cafe」で堪能できます。 眠りさえ忘れて踊り明かしたくなりそうなドリンクがそろう。写真右奥は「ビバ~マツケンサンバⅡ ワールドカフェ~オレ!」。絵柄は2種類(TOKYO PARADE goods&cafeプレスリリースより) 情熱的なサンバと時代劇という、一見するとミスマッチな世界観から生まれたマツケンサンバ。まばゆく陽気なメニューを食べながら江戸の街に思いをはせてみてはいかがでしょうか。 オリジナルグッズショップはカフェ予約なしで入場できる(※5月12日~15日以降。入場制限がかかる場合あり)(TOKYO PARADE goods&cafeプレスリリースより)■日本橋クルーズ(R) 住所:東京都中央区日本橋1-9(日本橋船着場) 電話:03-5679-7311(10:00〜17:00) 定休日:水曜(祝日の場合翌日休) 料金:【お江戸TOKYOクルーズ45分】平日1,500円/土日祝1,700円 【お江戸TOKYOクルーズ60分】平日2,000円/土日祝2,200円 【神田川クルーズ(R)】平日2,500円/土日祝2,800円 【東京湾クルーズ】平日2,000円/土日祝2,200円 【サンセットクルーズ】平日3,500円/土日祝3,800円 アクセス:東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅B6出口より 徒歩3分 都営浅草線、東京メトロ銀座線・東西線 日本橋駅B12出口より徒歩5分 ※その他予約等詳細は公式サイトをご確認ください ■戸山公園 住所:新宿区戸山1~3丁目、大久保3丁目 TEL:03-3200-1702(戸山公園サービスセンター) アクセス:東京メトロ副都心線 西早稲田駅より徒歩6分(大久保地区)・徒歩8分(箱根山地区) 東京メトロ東西線 早稲田駅より徒歩10分(箱根山地区) 都営大江戸線 若松河田駅より徒歩15分(箱根山地区) JR・東京メトロ東西線 高田馬場駅より徒歩7分(大久保地区)、徒歩21分(箱根山地区) JR山手線 新大久保駅より徒歩10分(大久保地区)・徒歩25分(箱根山地区) ■ビバ ~マツケンサンバⅡワールドカフェ~オレ! 開催場所:TOKYO PARADE goods&cafe 住所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ6F TEL:03-5679-7311(10:00〜17:00) 開催期間:2023年5月12日(金)~6月26日(月) ※5月26日(金)のみ16:00閉店 営業時間:11:00〜21:00(L.O. 20:00) アクセス:東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅B6出口より徒歩3分 都営浅草線、東京メトロ銀座線・東西線 日本橋駅B12出口より徒歩5分 ※予約等詳細は公式サイトをご確認ください
- スポット
- 八丁堀駅
- 日本橋駅
- 早稲田駅(メトロ)
- 有楽町駅
- 東京駅
- 渋谷駅
- 西早稲田駅