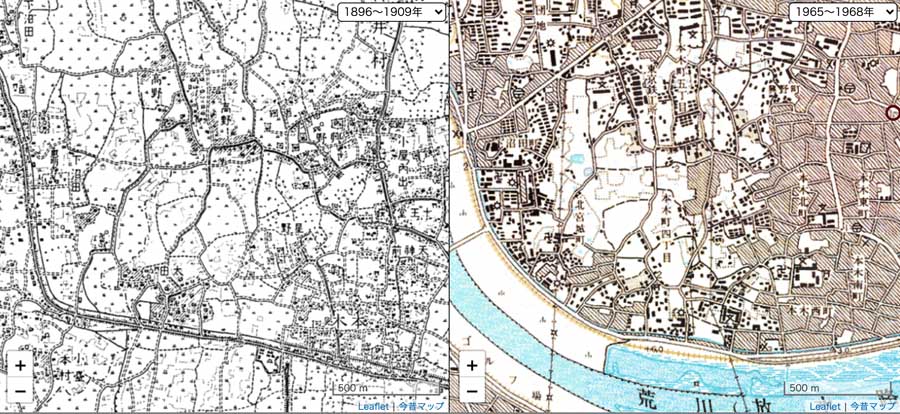ひとたび聞けば、たちまち江戸日本橋のにぎわいがよみがえる『三井の大黒』【連載】東京すたこら落語マップ(5)
落語と聞くと、なんとなく敷居が高いイメージがありませんか? いやいや、そんなことないんです。落語は笑えて、泣けて、感動できる庶民の文化。落語・伝統話芸ライターの櫻庭由紀子さんが江戸にまつわる話を毎回やさしく解説します。落語でおなじみの左甚五郎が登場 節分を控え、いよいよ新旧暦ともども春がやってきます。今回は、2020年の干支(えと)であるねずみがお仕えする大黒さまにちなんだ、おめでたい噺(はなし)の「三井の大黒」で、お江戸日本橋へ出掛けてみましょう。 200年前の日本橋を描いた絵巻物『熈代勝覧(きだいしょうらん)』の中の三井越後屋。三井越後屋は三井財閥の源流となった(画像:櫻庭由紀子) この演目に登場するのは、講談・浪曲・落語でおなじみの名人・左甚五郎(ひだり じんごろう)。飛騨高山から修行するべく、京都伏見、大阪、東海道の名所や宿場を転々とし、江戸に到着したところからお話は始まります。 ※ ※ ※ 飛騨の名工・左甚五郎。その作品には魂がこもり、命ないものに命を与え、鷹は飛び立ち鯉は泳ぎ始めるという。 さて、その甚五郎。江戸の大工はいかなるものかと、神田今川橋を渡った銀町(しろかねちょう)の普請場(建築現場)を通りかかった。威勢が良いものの、技術はどうも雑にみえる。思わず口に出してしまい、甚五郎は大工たちに袋だたきに遭ってしまった。 そこにやってきた、棟梁(とうりょう)・政五郎。大工たちをたしなめつつ甚五郎に素性を聞いてみると、「飛騨からやってきた番匠(大工)」という。大工ならちょうど人手が足りないから居候でやってみないかと誘いつつ、飛騨といえば名人甚五郎を知っているかと聞いてみると、「つまらん」という答え。甚五郎としてみると、名乗る前に名人と言われてしまったものだから具合が悪い。「ぽん州」と名付けられ、橘町(たちばなちょう)の政五郎の家へ厄介になることになった。 腕は立つが酒を飲んでゴロゴロ腕は立つが酒を飲んでゴロゴロ 次の日から普請場に連れていかれることになったのだが、大工たちは甚五郎に下見板(家の外側の下見に張る板)を削らせるだけ。甚五郎は、削った2枚の板を合わせて水に漬け、剥がせるものなら剥がしてと渡すが、ぴったりと張り付いていて剥がすことができない。ぽん州は「無理に剥がすとやけどをするぞ」と笑って帰ってしまった。 政五郎は大工たちからこの話を聞き、ぽん州が腕の立つ大工だと知る。そこで「江戸の大工は上方(関西地方)と違い仕事が粗い。ここにいても修行にはならないが、年末につきいろいろ準備してやれないから、春になるまで遊んでいると良い」というと、それから甚五郎は酒を飲んでゴロゴロするようになった。 業を煮やした政五郎は、上方の大工は彫り物(彫刻)が得意だと思い出し、「江戸の大工は年末に大黒さまとか縁起の良いものを掘って、市に出して内職にする」と甚五郎にも勧める。 そこで甚五郎は、江戸に来る前に日本橋の越後屋から「運慶作の恵比寿と二神像となるよう」と大黒の制作を依頼されていたことを思い出した。早速、二階でコツコツと仕事に取り掛かる。 大黒は後ずさりするほどの完成度 やがて二階から下りて来ると「風呂へ」と出て行ったぽん州。政五郎がどれだけ大黒が彫れたのかと二階へ上がってみると、たった一体。三寸ほどのものに布がかけてある。かけてある布をそっとあげてみると、陰が陽へ返って光があたった大黒が政五郎をみてニヤリと笑った。 政五郎が後ずさりすると、下から声がする。降りてみると越後屋からの使いがいて「甚五郎先生から大黒さまが彫りあがったと手紙をもらった」という。甚五郎がいるはずもない、と言いかける政五郎は、ぽん州が彫ったであろう大黒を思い出しハッとする。 そこに帰ってきた甚五郎。名乗れなかった理由とわびを政五郎に伝え、運慶作の恵比寿についていた「商いはぬれ手で粟(あわ)の一つ神(ひとつかみ)」に「護らせたまえ二つ神(ふたつかみ)達」と下の句を付けた。 神がふたつとなり、つかみもふたつ。三井の大黒というおめでたいお話(3代目桂三木助)。 日本最初の百貨店・日本橋三越本店日本最初の百貨店・日本橋三越本店 甚五郎に大黒さまを依頼した「越後屋」とは、言わずと知れた現在の「三越」。江戸本町1丁目(日本銀行本店付近)に「越後屋三井八郎右衛門」として創業し、現在の場所である日本橋室町(当時は駿河町)に移転しました。 日本橋三越本店の地下通路に展示している「熈代勝覧(きだいしょうらん)」絵巻には日本橋から今川橋までが描かれ、当時のにぎわいを見ることができます。 越後屋には「呉服賜物品々」と書かれた看板と井桁に三の紋。現在のマークは丸に越ですが、こちらは1904(明治37)年の「株式会社三越呉服店」設立時に改められたものです。 日本橋三越本店(画像:櫻庭由紀子)●日本橋 水の都であった江戸。水運の拠点であり東海道や中山(なかせん)道の始点であった日本橋は、魚河岸や商家があり金融、商業、交通で栄えた江戸の中心でありました。 現在でも、「日本道路原標」と「日本橋魚河岸発祥の碑」で当時の名残を見ることができます。周辺には三越を始めとした江戸時代からの老舗も多く、レトロと現在が混在。 日本橋の上を走る首都高は地下化の構想が進められており、日本橋に空がもどる日がやってくるかもしれません。 ●今川橋跡碑 甚五郎が渡った今川橋。神田八丁堀または竜閑川に架かっていたとされています。現在は埋め立てられ、交差点名と跡碑にしかその名前は残っていません。 今川橋近くの普請場があった銀町は、本銀町といい現在の中央区日本橋本石町4丁目、日本橋室町4丁目、日本橋本町4丁目あたりをいいます。 政五郎の家があった橘町は、現在の東日本橋3丁目・日本橋久松町。越後屋(日本橋三越本店)までは1キロほどなので、小僧の足でひとっ走りといったところでしょう。甚五郎が小僧に使いをやって風呂に入っている間に越後屋の番頭がやってくるという距離感です。 ●日本橋三越本店 日本最初の百貨店であり重要文化財に指定されている日本橋三越本店の前身が、甚五郎に大黒を依頼した越後屋です。 「店前現銀売り(たなさきげんきんうり)」という、現在では当たり前の店頭売りを初めて行い、呉服を庶民でも購入できるものとしました。三井家は呉服商と同時に両替店を開店し、こちらは現在の三井住友銀行(千代田区丸の内)へと発展します。 日本橋三越本店では、店内ツアーがあり無料で参加できます。現存する1914(大正3)年に設置されたおなじみのライオン像、1960(昭和35)年に建立された天女像、1930(昭和5)年に輸入されたパイプオルガン、1928(昭和3)年に開設されたアールヌーボー調の三越劇場、さらには内装の大理石に含まれる化石など、見どころがたくさん。三越劇場では1953(昭和28)年から「三越落語会」が開催されています。 左甚五郎は架空の人物?左甚五郎は架空の人物? 左甚五郎は名を利勝といい、江戸初期に活躍した彫刻の名工です。架空の人物とも実在したともされ、真偽は不明。 全国には甚五郎作と言われる作品が100余り残されており、日光東照宮の眠り猫、上野東照宮(台東区上野公園)の昇り竜と降り竜、知恩院が有名です。 知恩院の御影堂の屋根には「甚五郎の忘れ傘」は知恩院七不思議のひとつ。中には時代的に計算が合わないものも甚五郎作とされており、名工の代名詞として左甚五郎の名が伝わっていったのかもしれません。 左甚五郎の「左」とは、「左利き」「右に出るものがいない」「その腕を嫉妬したものから右腕を切り落とされた」などさまざまな説があります。 講談で読まれているのは「右腕切り落とし」説。もっとも、腕をねたまれ命を狙われるというのはお芝居お約束の展開でもあり、本当のところは謎のままです。 歌川国芳『名誉右に敵なし左甚五郎』(画像:櫻庭由紀子) 左甚五郎は、講談・浪曲・落語等の演目で語られており、講談では甚五郎の作品と生涯を追う一代記となっています。 落語の演目では、本作「三井の大黒」のほか、浪曲師・廣澤菊春原作の「竹の水仙」「ねずみ」「四つ目屋」が有名。浪曲でおなじみ「掛川の宿」は笑福亭鶴光、「叩き蟹」は三遊亭圓窓により落語に改作され演じられています。 「四つ目屋」は、さすが甚五郎が作ったものは魂がこもっているわけだと膝を打つ艶笑小噺です。枕で使われることもありますが、落語を聞く女性のお客さまが多くなった昨今では、あまりかける機会がないかもしれません。 桂三木助最後の一席桂三木助最後の一席「三井の大黒」は、1時間弱の長講にして甚五郎のとぼけた感じと江戸っ子の口調を演じ分け、ストーリーのクライマックスの政五郎が、大黒さまを見つけて息を飲む様子を説明的に語ることなく演じるという、体力と技術の両方を必要とする難しい演目です。 この演目を得意としていたのが、3代目桂三木助。三木助最期の演目としても知られています。 がんに冒されていた三木助は、正座することができないため見台(書物をのせて読む台)で足を投げ出して演じたと伝えられています。この高座の音源が残されていますが、音だけにも関わらず、江戸の真ん中で浮き上がる甚五郎と、大黒を見つけた政五郎の驚きと恐れが目に見えるようです。まさに名演。映像が残されていないことが悔やまれます。 三木助のほかに、三遊亭圓生の高座も有名です。圓生は甚五郎を「ぽん州」ではなく「ぬうぽう」としており、甚五郎のとぼけた面白さに視点をおかず、名工が爪を隠してあえてとぼけた風を装っています。特に、政五郎が甚五郎が彫った大黒と対面するシーンは、息遣いや「間」で総毛立つ政五郎を描写。完璧で見事な高座です。 物語の三木助、描写の圓生。ふたつの「三井の大黒」を聴き比べてみるのも面白いでしょう。
- ライフ
- 三越前駅
- 新日本橋駅
- 日本橋駅