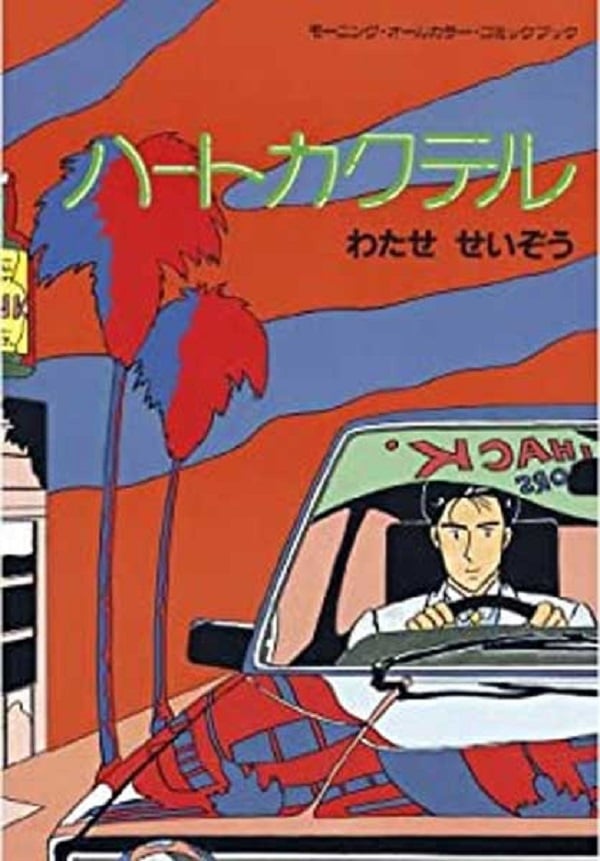人気作品「孤独のグルメ」の主人公・井之頭五郎を支える、揺るぎない「7つのテーゼ」とは
月刊誌に連載 当初は話題にすらならず 人気シリーズになった松重豊さん主演のテレビドラマ「孤独のグルメ」(テレビ東京系)。2019年10月からはシリーズ第8弾の放映も決まり、ふたたび話題となっています。 2018年4月6からテレビ東京系で放送された「孤独のグルメSeason7」(画像:KADOKAWA)「孤独のグルメ」は、松重さんが演じる輸入雑貨商の井之頭五郎(いのがしら ごろう)が、営業先でふらりと立ち寄った店で食事をする様子を描く物語で、久住昌之さんと谷口ジローさんによる同名の漫画作品が原作です。現在の圧倒的な人気とは裏腹に、連載が始まった当初、漫画はまったくといってよいほど話題になっていませんでした。 1994(平成6)年6月から始まった原作漫画の連載誌は、扶桑社(港区芝浦)が発行していた月刊誌「PANjA」。この雑誌は「SPA!」の2代目編集長だった渡邊直樹さんが編集長を退任後、新たに創刊した雑誌でした。 連載開始は、「PANjA」1994年10月号「SPA!」は1988(昭和63)年6月に「週刊サンケイ」がリニューアルして誕生した雑誌です。新聞社の発行する週刊誌の硬さを取り払うことを目指していましたが、当初は伸び悩んでいました。 それを企画やデザインの全面刷新で、若者にウケる雑誌にシフトさせたのが渡邊さん。流行語「オヤジギャル」を生み出した中尊寺ゆつこさんや宅八郎さんなど、多くの人物が脚光を浴びました。 「東京都台東区山谷のぶた肉いためライス」のイメージ(画像:写真AC) その勢いで創刊された「PANjA」で「孤独のグルメ」の連載が始まったのは、1994年10月号。最初のエピソードは「東京都台東区山谷のぶた肉いためライス」でした。 人気は「B級グルメのメジャー化」と連動人気は「B級グルメのメジャー化」と連動 しかし、連載はまったくといってよいほど話題になりませんでした。なぜなら、掲載誌が売れなかったから。当時、筆者はリアルタイムで雑誌を買っていましたが、イメージは「SPA!」の月刊版。よくも悪くも、より濃厚なマニア受けする誌面が一部の読者にウケても、幅広い支持につながらなかったのです。 結果、「PANjA」は1996(平成8)年6月号で休刊。翌年の1997年に「孤独のグルメ」は単行本として発売されましたが、こちらもまったく話題になりませんでした。それがにわかに脚光を浴びるようになったのは、21世紀に入ってからです。 きっかけは、何人かの読者が作中でモデルとなった店を実際に探し当て訪問する、一種の「聖地巡礼」です。それが、知る人ぞ知る店を探索する「B級グルメのメジャー化」とシンクロする形で、現在の作品人気を生み出したのです。 「B級グルメ」という言葉は1985年からあった さて、今では当たり前のように使われる「B級グルメ」という言葉。おいしさはもちろん、安く庶民的で味のある雰囲気や接客の料理店や料理を指す言葉として広く使われています。そうした店を訪れることを趣味とする人は、限りがありません。 でも、その言葉は当初の意味とは大きく変わっています。「B級グルメ」の生みの親はフリーライターの田沢竜次さん。主婦と生活社(中央区京橋)が発行していた情報誌「月刊アングル」で田沢さんが連載していた、「田沢竜次の東京グルメ通信」を「東京グルメ通信」として単行本化するときに、帯に「B級グルメの逆襲」という言葉を記したのが最初です。時に1985(昭和60)年12月のことでした。 「特定の店の常連にならないように」「特定の店の常連にならないように」 この本の冒頭では「B級グルメ宣言」と称して、 1.腹ぺこ精神 2.限られた予算で最大の効果をあげる食の知恵 3.恐怖感 4.権威にびびらない 5.細部へのこだわり 6.歩くこと 7.脱ブランド、反ファッション の計7つのテーゼを掲げています。 アウトローなノリなくして「孤独」のグルメは語れない(画像:写真AC) 実は「孤独のグルメ」も作品の意図は、このテーゼに沿ったものでした。原作者の久住昌之さんは、青土社(千代田区神田神保町)が発行する「ユリイカ」2011年9月号のインタビューで、こう語っています。 「「孤独のグルメ」の連載当初、テレビでも雑誌でもグルメブームで食べ歩きとかがすでに流行っていた。ラーメンやカレーとか、手打ち蕎麦とか。編集者は、それにちょっとウンザリしていて、違う方向性をみせられないかということで、ぼくに依頼してきたと思うんですね」 なるほど、原作でそこはかとなく描写される井之頭五郎のアウトローなノリは、この精神性にあるのでしょう。原作やドラマのコミカルさを笑ったり、描かれた店へ行列するようでは、まだ作品を理解し切れていない――私はそのように思います。 前述の田沢さんとある取材でお会いしたとき、「特定の店の常連にならないように気をつけている」と話されていたのが印象に残っています。まさに「B級グルメ」の体現者といえるでしょう。
- ライフ