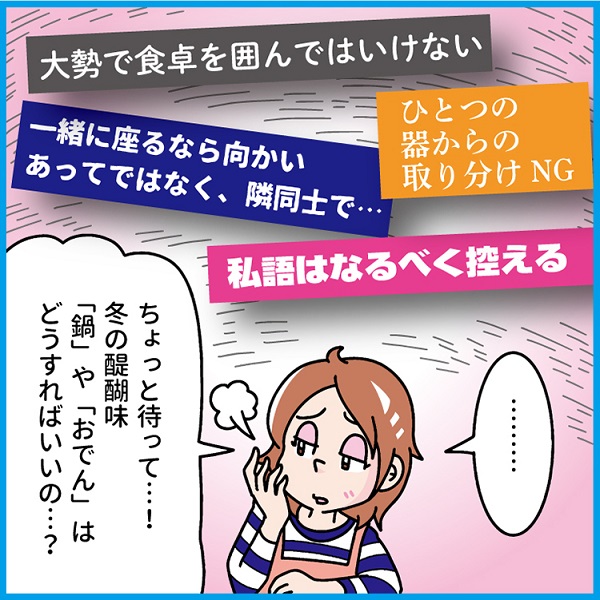再開発めざましい大井町 かつてはあちこちで水が湧き出ていた!
昭和と令和が融合した大井町 かつて、品川区の大井町駅西口から少し歩いたところに「大井武蔵野館」という映画館がありました。 この映画館は自ら「名画座最後の砦(とりで)」をうたっており、かなりマニアックな上映プログラムを組んでいました。少し背伸びしたい「文化系大学生」には欠かせない場所でしたが、残念ながら1999(平成11)年1月に閉館し、跡地はマンションに。つくづく月日が流れるのは早いと感じます。 現在は昭和の雰囲気を残しつつも、再開発されたエリアが目立っています。 水が豊富だった大井町 そんな大井町ですが、過去を見ると、1834(天保5)年から1836年まで出版された地誌『江戸名所図会』に、水量の豊富な「大井の井」という泉が描かれています。 『江戸名所図会』に描かれた「大井の井」(画像:品川区) 水量こそ減っているものの、大井の井は光福寺(品川区大井6)に現存しています。江戸時代の大井村は武蔵野台地の端を含んだ、海に面した農村地帯で、あちこちに泉が湧いていたのです。 なお「大井の井」の「大井」が大井町の地名の由来となったと伝えられています。 さかのぼること340年前さかのぼること340年前 そんな水の豊かな大井では水神の信仰が盛んでした。 その信仰の中心が水神社(大井の水神。南大井5)です。この神社は大井鹿島神社(大井6)の境外末社で、社殿はなく溶岩を積み上げた洞窟という少し変わった神社。ここには「柳の清水」と呼ばれる湧き水がかつてありました。 始まりは1685(貞享2)年。この土地に干ばつが起こったとき、常林寺(現・来迎院〈大井6〉)の住職・栄住が大井村の名主である桜井伊兵衛と大野忠左衛門を願主に、九頭龍権現を勧請(かんじょう。神仏の分霊をほかの場所に移し祭ること)。そうしたところ、水が湧き出したそうです。 『鹿嶋大明神起立縁起』によれば、このときに湧いた柳の清水はその後に枯れかけたものの、栄住がさらに鹿嶋氏神、龍神などを勧請したところ、再び水が湧いたといいます。この水を「竜神守護之名水」であるとして、水神・九頭龍権現を石造の堂宇に祭りました(『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』)。 栄住という僧侶の祈りがもたらした御利益や、僧侶が神を勧請するという神仏習合が興味を呼ぶエピソードが印象的です。 柳の清水については、江戸時代後期の地誌『新編武蔵風土記稿』にも「旱打續きし時も涸ることなしといふ」と記されています。 江戸時代は常林寺が水神社を管理していましたが、いつからかその手を離れ、現在は「大井水神町会」が管理しています。 町会名はこの水神社一帯が1873(明治6)年の地租改正以降、水神下となり、その後の住居表示まで水神町と呼ばれていたことに由来します。 1931(昭和6)年発行の地図。水神下の記載がある(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) 都心化が進んだ東京でも、伝統を引き継ぎ地域で管理されている神社は少なくありません。この水神社もそのひとつで、神社では毎年元旦祭に始まり、5月には春祭り、10月には秋祭りが行われます。 元旦祭では、水神社にちょうちんを掲げてお神酒などが振る舞われ、今でも多くの参拝客が訪れます。最近は6月に開催される「大井水神社 ホタルの夕べ」も人気のようです。 ちなみに、品川区の文化財の解説によると歯痛に御利益があるそうですが、なぜそんな御利益があるのかは、わかりません。 水量は減少も残る歴史水量は減少も残る歴史 枯れない泉としてあつく信仰されてきた水神社ですが、残念ながら現在ではほとんど枯れています。 『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』によると、2006年の夏にはわずかに水面が揺れていた(注:水量が豊富に湧いていた)といいますが、その後は増えたり減ったりが繰り返されているようです。原因は、周辺の宅地化によるものと考えられます。 ただ、御利益が失われてしまったのかと思いきや、近くにあるJR東海道本線をくぐる「桐畑地下道」からは今も豊富に水が湧いており、水をためた場所で金魚が飼われています。神様の都合で少し位置が移動したのかもしれません。 品川区大井にある「桐畑地下道」(画像:(C)Google) 都市化した今では想像もできませんが、かつてのこの地域ではあちこちから水が豊富に湧いていたのです。
- 未分類